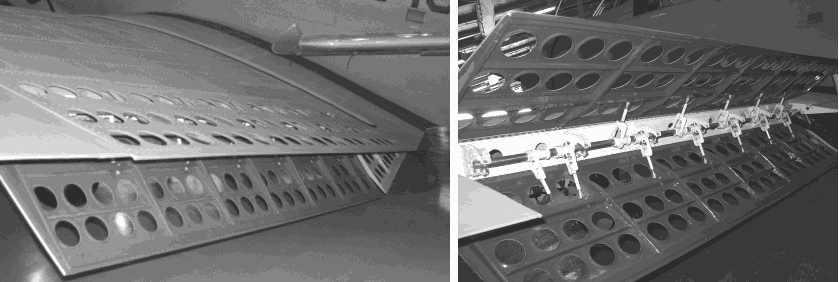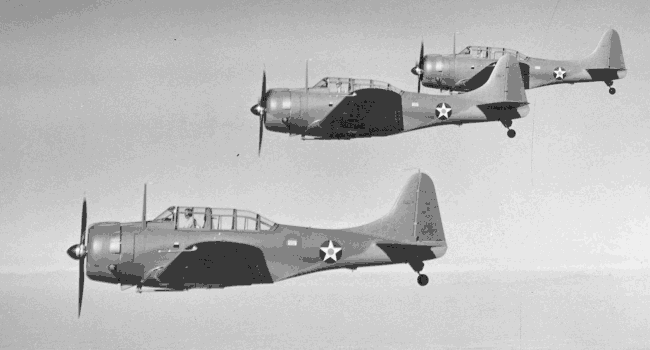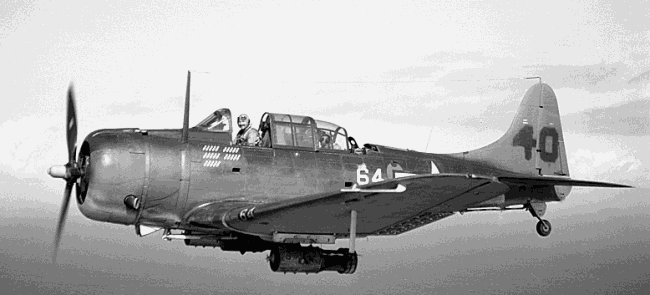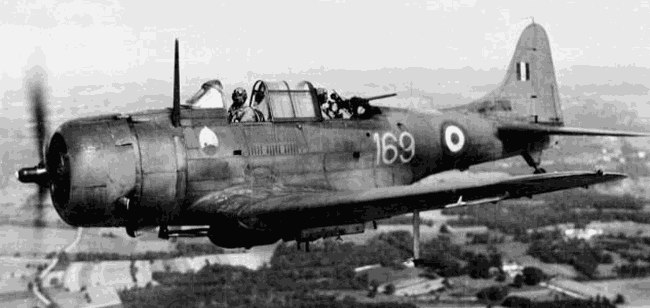この1機 <SBDドーントレス>
左:BT−1のエンジン、P&W R−1535系 右:SBDのエンジン、ライト R−1820系

R−1535は二重星型14気筒の800馬力級エンジン。 日本の「栄」のようなスペック
だが排気量はわずかに少ない。 それに比してSBDのR−1820は星型9気筒で、見た目
はスカスカなので非力に思えるが排気量は「栄」より大きく、単列式ゆえ信頼性も高く、整備
性も良いように見える。
ただし、二重14気筒以上の排気量を単列9気筒に収めるので、どうしても直径は大きくなる。
それでもターボ過給機装備型はB−17などにも採用され、初期〜中期の戦力を支えた。
後にダブル・サイクロン経由でB−29のデュプレクス・サイクロンに進化する。
引き込み脚の採用
当時の艦上機は、複葉機もまだ多く、単葉というだけでも高性能に思えた。
その上、原型のBT−1は1935年に初飛行し、直系のSBDは1939年に量産開始。
これは、1938年に初飛行し1939年から制式採用された、カウンターパートの99艦爆
と対比した時、いかに引き込み脚が先進的な設計かわかる。
日本海軍初の全金属製低翼単葉引込脚の艦載機97艦攻ですらも、1935年に試作発注がな
された状況なのだから。

いかにも質実剛健そうで武骨な印象の脚回り。(現在の博物館内)
油圧駆動で作動し、操作から10秒ほどで主翼内に引き込まれる。
アブソーバー部分はカバーに覆われるが、タイヤは外から見える状態のままである。
この主脚は機体の重量に比して頑丈にできており、トラブルがない限り通常の着艦ではまず
破壊されないほどで、場合によっては爆弾を搭載したままでも着艦可能とされるほど頑強。
ダイブブレーキ
急降下機動は小型機でも非常に難しい機動で、大型機なら30度でも急降下である。
それを60度以上の角度でダイブするのだから尋常ではない。
70度にも達するともはや操縦困難となり、それ以上となると操縦者の体が座席から浮いて
しまうなど危険な状態となる。
そして、急降下時に速度が速くなり過ぎれば空中分解や引き起し不能の事態を招く。
その過速度を抑える装置がダイブブレーキと呼ばれる空力制動装置である。
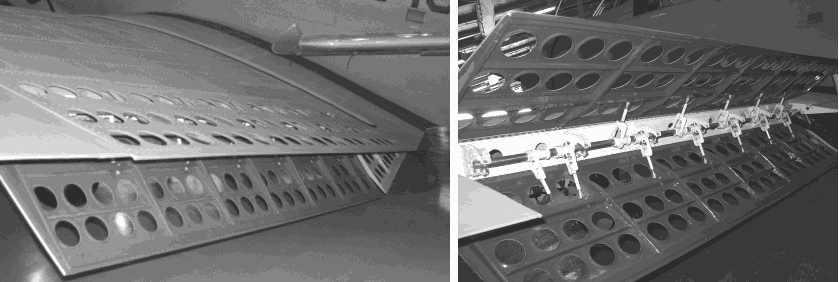
これらはSBDのダイブブレーキ兼フラップ(高揚力装置)である。(現在の博物館内)
左が着陸・着艦時の状態で、主翼後方下面部だけが下に降りる。 いわゆるスプリットフ
ラップである。 主翼上面の空気の流れを極力阻害せず、主翼下面の揚力の増加は大。
この形式は抵抗となる「抗力」も大きくなるが、SBDの場合はそれを逆手に取った。
右が急降下機動時のダイブブレーキの状態で、主翼上面部も上向きに開く。
これらは油圧で作動するが、不具合が生じた場合は手動で作動させることもできる。
またどちらの状態でも胴体下部分のフラップは開状態となる。
SBDの場合、70度の急降下時にダイブブレーキ使用した場合、440km/h程度で
降下するが、中には480km/hに達した事もあるという。
高度5000mからの降下でも30秒以内に引き起こさないと海面突入の危険が出てくる。
余談だが、戦争末期の日本の特攻機の操縦者に対し、上官が「上方から垂直に降下し、煙突に
真上から突入するように」との訓示を垂れた事がある。 こういう現場を知らない者の指示で
実戦経験のない速成の操縦員が初めて出撃するのだから、その責や何処に。
海軍以外でも運用された機体
SBDはA−24のコードでアメリカ陸軍でも使用された。
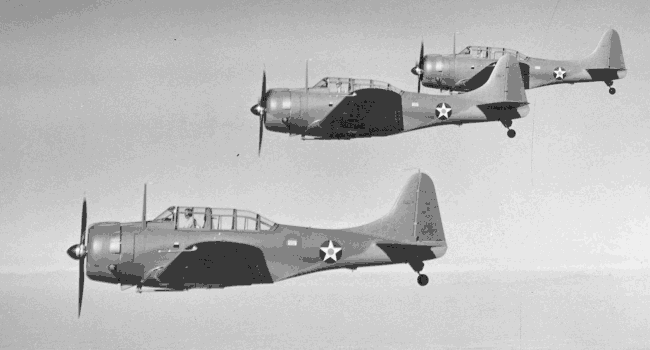
陸上での運用を前提としているため着艦フックが外されているが、基本的にはSBD−3。
アメリカ海兵隊でも装備機とされ、SBD−5以降の生産機はほとんどが海兵隊向け。
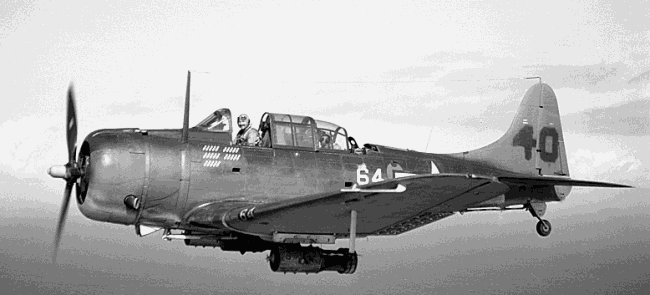
大戦中はイギリス軍にも供与されていた。
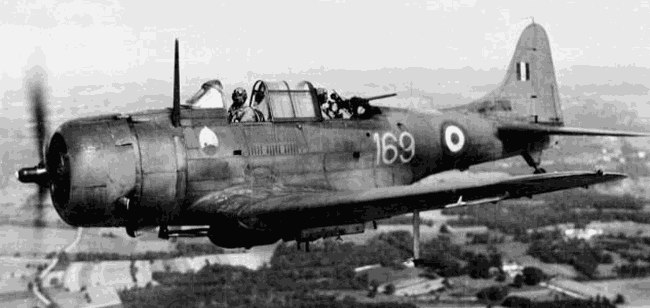
次項
特集見出しに戻る